←第9回講義内容へ
←情報環境論シラバスへ (10)情報環境におけるコミュニケーションとコラボレーションの実際(その2)
2002,12,6 第10回
<前回の課題の説明>
「Netmeeting をCSCLの分野でどのように活用できるか。」CSCL…コンピュータを利用した共同学習
共同性、状況性を重視した学習理論 ⇒ 既存テクノロジー
ネットワークテクノロジーの発達が背景 新規アプリケーション◎Netmeetingの機能
・カメラ
・共有ホワイトボード
・共有アプリ
・共有デスクトップ
・チャット◎Netmeetingの特徴
分散。
・遠隔地
・ひきこもり ⇒ 生徒
・自宅学習・偉い人 ⇒ 先生
・外人◎よくある間違いの例
× 1対1の学習環境
→ 1対1にみえるだけ。
× 英語学習
→ ただの英語学習だったらNetmeetingでなくてもできる
× 学生参加
→ ただし心理的負荷の低減を加味しているなら○
↓
匿名性、社会的手がかり(地位、立場、年齢)→失われる→自由かつ積極的発言◎良いなぁと思った例
・授業意識の向上を考えていたもの
・心理的負荷の低減を考えていたもの<討論支援>
「結果を導く」自体を支援○GRAPE(富士通国際研)
複数のユーザーが入力した仮説や評価項目を主観的評価木(モデル)を作成し、結論導く<相互作用システムの分類(Kramer & Pinsonneault)>
・グループのコミュニケーションを支援するシステム(GCSS)
・意思決定を支援するシステム(GDSS)
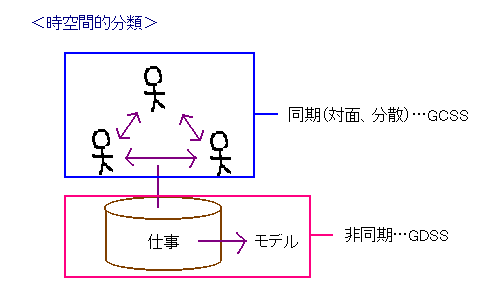
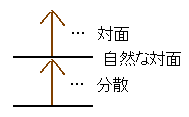
●GCSS
・コミュニケーションの障害を取り除く(分散)
→自然なコミュニケーションに。
・より円滑なグループコミュニケーションを実現(対面)
→仕事の質を対面集団のものより良くする
○対面集団でのコミュニケーション
・メンバーが直接的に相互作用するグループのコミュニケーションの特徴
(McGrath & Hollingshead)
・全てのメンバーが全てのチャネルで時間差0で。
・一時点で発言できるメンバーは一人だけ
・現時点の話者は次の話者をある程度選択可能
・メンバーの発言量は均等ではない
・話者はさまざまなチャネルを通じて発言の終了を示す
・各発言がそれ以前の発言と論理的、心理的に関連していることを期待している
・即時性、発言機会の制約と偏り****** 課題 ******
授業で説明しなかったグループウェア(実際にある商品、実際にある研究)を説明する。
同期分散、非同期分散、同期対面をそれぞれ一つずつ。
←第9回講義内容へ
←情報環境論シラバスへ