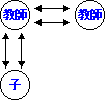第5回 教員同士の連携
27/11/2002
連載第5回
【今日の授業内容】
教員の学校教育相談に関する関心レベル
レベル1:相談担当者の考えや提案に賛成し一緒に積極的に行動してくれる人
レベル2:学校教育相談に理解・賛成はしてくれるが、行動はしてくれない人
レベル3:学校教育相談に反対だが、存在理由は理解してくれる人
レベル4:学校教育相談に無意味で反対だとするが、敵対はしない人
レベル5:学校教育相談に無関心な人
レベル6:学校教育相談に敵対的な人
学校教育相談へのネガティブな態度には次のようなものがありえる
1.「相談」というような姿勢では規律が保てない、甘い
2.個別にじっくり対応するだけの時間が与えられていない
3.教育相談ができない、苦手だ
4.自分なりのやり方でやっていける
● 教育相談は固定的なものか?
「どうしたの?」「ふーん、そうなんだ」 というような優しいものだけが教育相談か?
というような考えもある。
ポイントは 「敵対するものを敵にまわさないということです。」
2.教員同士が連携していくために
教員同士が連携できない要因は①時間がないこと、②専門性を盾に自分の縄張りを作ってしまいがちなこと。
大野(1997)は連携を作るきっかけとして校内研修会、つまり、勉強会と、広報活動が有効であると述べている。
3.コンサルテーション
専門家が専門家からアドバイスを受けること。
問題点:生徒担当者が専門家に聞くと「●●はやりましたか?」 「▽▽はしなくてhいけませんよ」などということになって、たとえ成功しても専門家がたたかれてしまって意味の薄いものになってしまう。
4.演習
相手のことを褒めてみよう!
ストレス解消法ということについて3分くらい話してみて、1分後にそのことについて相手を褒めてみるということ。
やってみて、実際、相手を褒めることが難しい。大げさすぎると相手を傷つけるし、地味すぎても・・・
5.付録
パワーアップの源としての「褒める」の難しさ
褒めることの多様性 『ねぎらう』や『認める』も含めて『叱る』も?
何を『褒める』と本当に褒めたことになるのか
7.参考文献
大野精一『学校教育相談ー具体化の試み』ほんの森出版、1997