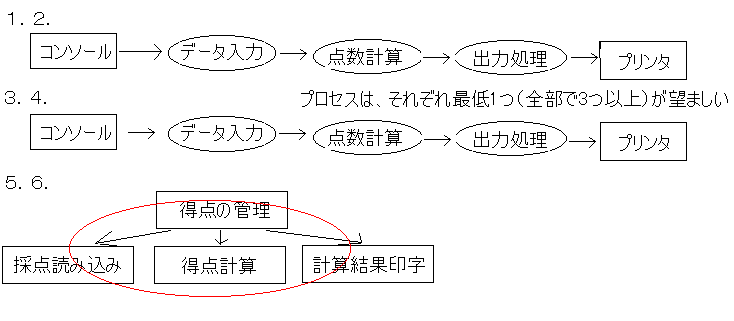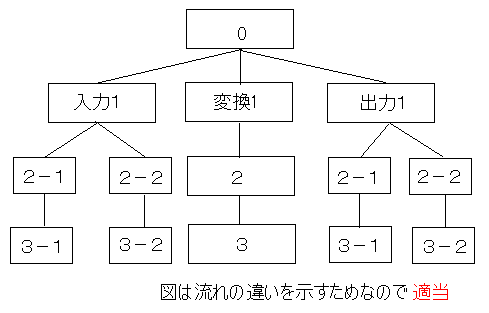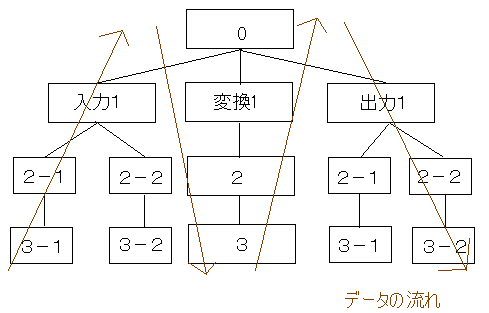6月21日のレポート
このレポートの採点A-
STS分割とはどのようなモジュール分割なのかを説明せよ。
また、トップダウン設計とはどのような点が違うのか考えて差異を述べよ。
Source 入力機能
Transform 変換機能
Sink 出力機能 というように、データの流れ順に
沿って、モジュールを分割する手法
STS分割は、システムの各機能(
不正確、入力、変換、出力)がきちんと定義され散る場合に有効であり、
上記のように、STS分割では、テー他の「入力」「変換」「出力」に
着目して、モジュールを分割する。
(データの流れは、要求分析の校庭で用いたDFDを用いることで分る)
STS分割の実行
1.3個以上のプロセスで表現する
2.主要なデータフローを見極める
3.データの変化に着目する
4.入力、変換「出力に分ける
5.モジュール分割を行う
6.下位モジュールに分割をする
図解が必要
テストの点数結果を、計算、整理するプログラムを例に手順を追ってみよう。(番号は実行に則している)
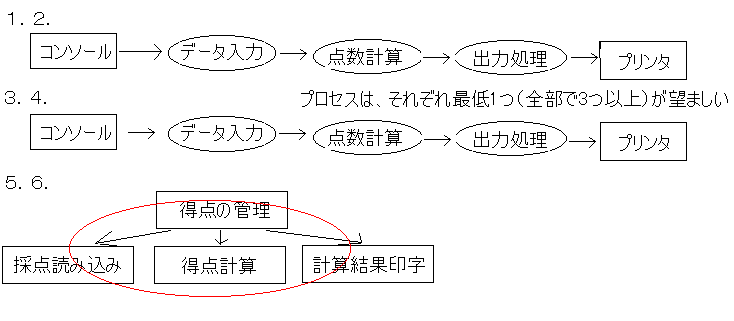
*プロセスが3つ未満の場合・・・各機能にできるだけ近いものを見つけて
無理やり3つ以上に分ける。
*プロセスが多数有る場合・・・・主要な流れのものに着目する(実行の2)
(あいまいであることが多く選定は難しい)
また、「入力」「変換」「出力」を的確にわける方法として、データの変化に着目する。
入力の場合はDFDのさいしょから、
出力の場合は最後からデータの状態を追っていき、
もとのデータがプロセス内の処理形式(元のデータとは分らない状態)になったところを境目とする。
そして、以前のモジュール分割ででたように、各モジュールのステップが50〜100位になるまで分割する。
その結果、階層構造のリストが出来上がる。
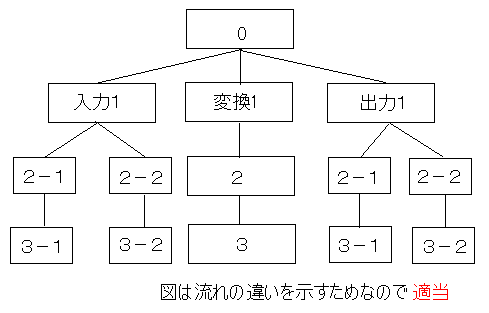
このような階層構造になるので有るが、
1.入力プロセスの下位階層から上へと上がっていく
2.変換プロセスを順番にこなして、再び戻ってくる
3.出力プロセスを上から下へと流していく
ので、
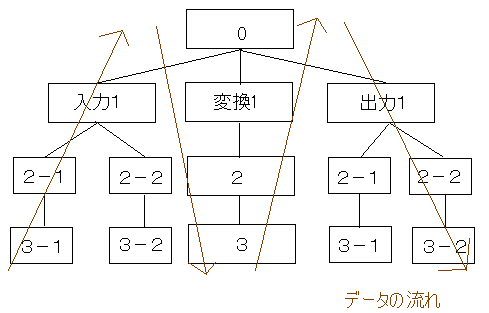
と、矢印のような流れになるので
トップダウン設計のように見えても、
常に上から行っていくのと(何の?)流れ方が違うので
注意が必要である。
トップダウン設計とSTS分割の違いの説明
前半はよく理解していると思う。もう一歩、???、まとめ方に工夫をすると、よくなる。
ソフトウェア設計学のTOPに戻る
2002年前期のツボプロジェクトのTOPに戻る