4月19日のレポート
このレポートの採点A−
ソフトウェアエンジニアリングとは何か、
また、どんな工程があり、どんな問題があるのかを説明しなさい。
1960年頃はソフトウェアは個人で作成していた。しかも、ソフトよりはハードに力が入っていて、ソフトの生産性、安定性は低かった。しかし、1960年代後半にはいると、利用者が増大、さらに、コンピューターの利便性によるソフトの巨大化により、個人芸では経済的負担が大きくなりすぎていたし、各人ごとに考え、様式が違いまとまりが無かった。
だから、ソフトウェアの技術や知識(経験の集積)を体系的にまとめて、生産等に活用する耐めに、ソフトウェアエンジニアリングは生まれた。そして、集団となり体系的にまとめた知識や技術により、
・利用者の要求を満足させるために知識を提供。
・開発、保守の生産性を高める手法の提供。
・ソフトの信頼性を高める手法の提供。
を、行い、全体的な生産性を向上させ、ソフトウェアの需要をできるだけ満たす働きをしている。
ソフトウェア開発プロセス
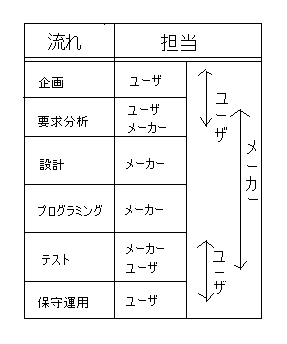 ・要求分析・・・・・・ユーザがどのような機能を求めているかを、ユーザとメーカーで話し合いを行い、メーカーで、きちんと把握し、目標を決める。
・要求分析・・・・・・ユーザがどのような機能を求めているかを、ユーザとメーカーで話し合いを行い、メーカーで、きちんと把握し、目標を決める。
↓
↓
・設計・・・・・・・・要求分析にしたがって、プログラムの全体的な構造を形作る。
↓
↓
・プログラミング・・・設計に従いここのプログラムを組んでいく。
↓
↓
・テスト・・・・・・・作られたものにはバグは無いか、テストを行い、バグを発見した場合は修正する。
問題点→→→→→工程毎に整理しておくこと
メーカーとユーザはお互いの仕事に詳しくないために、ソフトウェアに求められる内容に誤解が生じる。そして、誤解を残したままにすると、メーカーが最高だと思うソフトであってもユーザは全く満足できないということもある。そのようなことを無くすためには、両方の仕事に詳しい人がいればいいのだが、そう都合がいいわけはないので、要求分析をしっかりと行わないといけない。
設計において
プログラミングにおいては、複数人数で行うため、複雑で分りにくいフローチャートも好ましくない。保守の際にも多くの作業時間を要する。そのためにも誰にでも分りやすいものを作成することが重要である。
テストにおいて
さまざまな場合を考えて多くの工程をテストしなければならない。もしもテストが不十分であれば、製品の納品後に不具合が生じた場合に大きな問題になってしまう。
ソフトウェア設計学のTOPに戻る
2002年前期のツボプロジェクトのTOPに戻る
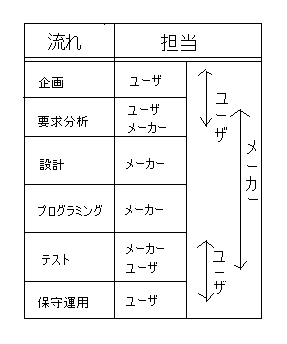 ・要求分析・・・・・・ユーザがどのような機能を求めているかを、ユーザとメーカーで話し合いを行い、メーカーで、きちんと把握し、目標を決める。
・要求分析・・・・・・ユーザがどのような機能を求めているかを、ユーザとメーカーで話し合いを行い、メーカーで、きちんと把握し、目標を決める。