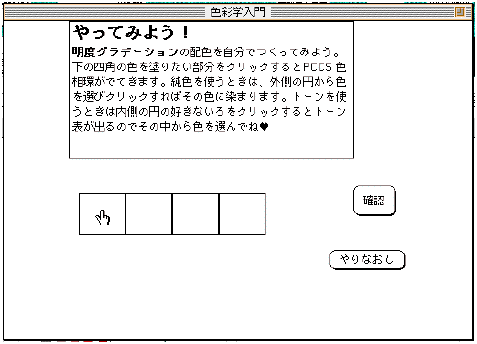
Design and Development of CAI Courseware "Intrduction to Colorogy"
〜Learning Coloring by Experience〜
9351186 横内 美奈
鈴木 克明 先生指導
1-1 はじめに
近ごろ、色に対する人々の関心が高まってきている。地球を大切に、という発想から生まれたアースカラーの流行。ストレス・マネジメントの現場で応用されている、色による心理療法。企業のイメージカラーなど…。
このように色に対する知識の需要が高まっているにもかかわらず、それを学習するための教材というのはまだまだ少なく、専門的な難しいものというイメージが強い。そこで本研究ではコンピュータ教材の長所を生かしながら、学習者が色というものへの興味を深め、色をより身近なものと感じ、様々な形で実生活に役立てることが出来るようになることを目的とした。
1-2 色彩学とは
色彩学とは様々な色の決まりを学習するというもので、1995年度よりこれまでの「カラーコーディネーター試験」が、「ファッションコーディネート色彩能力検定」と名前を変え、文部省の認定を受けたことからもわかるように、近年大変注目されている。カラーコーディネーターは、ファッション、インテリアの分野はもちろん、国や地域の環境作り、病気治療にあたる室内の見直しから、実際の治療にいたるまで、広い分野で活躍している。
1-3 CAI教材にする理由
CAIとは(Compuer Assisted Instruction)の略称で、コンピュータが教えるべき情報と教授の流れの情報をも持っていて、学習者がそのコンピュータと対話的に勉強していけるシステムのことである。CAI教材では、たくさんの色が表示可能なため、微妙な色の差や、視覚効果の表現も効果的である。また、色を染めたり消したりが容易なので、実際に学習者が色を染めて解答するような、何通りも答えのある問題にも対応できる。
色は目で見て知るもので、色の勉強の入門はまず視覚体験が第一である。ところが、既存のプリント教材の多くは、色刷りが貧弱で文字解説でそれを補おうをしていたり、問題もほとんどが選択形式になっているため、概念がわからなくても答えを暗記してしまうことがある。そこで上に述べたCAI教材の特徴を利用することによって、プリント教材の弱点をカバーした教材を作成することにした。
教材の全体構成を表1に示す。本研究では大島(1993,1995)をもとに検定で扱う内容に沿った形で教材を作成した。本研究は副題にもあるように「配色の体験学習教材」の設計と開発なので、配色について学習する3 章の「色の組み合わせのいろいろ」がメインの部分となる。普通プリント教材で配色の概念(ルール)を学習する場合、問題の形式は主に、予め提示された配色の中から正解を選択するという形になってしまうが、 この教材では1-3で述べた特徴を生かし、学習者が好きな色から自由に配色するという形式を採用した。
表1.教材の全体構成
| 1,色ってなーに? | 光との間から 光の色 |
| 2,色のきまりのいろいろ | 光と色料の三原色 混色 三属性 三つの色立体 |
| 3, 色の組み合わせのいろいろ | グラデーション トーン・オン・トーン トーン・イン・トーン カマイユ フォカマイユ 角度配色 セパレーション アクセント コントラスト レピテーション ナチュラル ハーモニー コンプレックスハーモニー |
| 4,色とこころ | 見え方感じ方 対比 |
| 5,目に起こる現象 | 明所視・暗所視・薄明視 順応 ベンハムトップ プルキニエ現象 演色性 同化現象 色の視認性 色の誘目性 カラーフリッカー グレア現象 残像現象 |
メインとなる「配色の体験学習」部分の実際に自分で配色する様子を明度グラデーション配色を例にして図2に示す。
まず、 図2-1の画面から色を染めたい四角をクリックする。
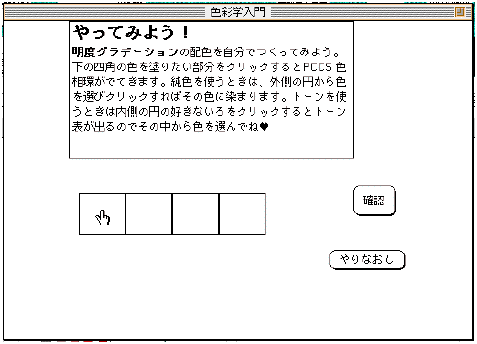
図2-1やってみよう画面
すると図2-2のような色相環(色のパレット)が出る。ここに表示されているのは全て純色で、このうち偶数番号の色にはそれぞれ12色のトーンがある(図2-3)。純色(図2-2)をそのまま使いたいときには、外側の円から好きな色を選んでクリックするとその色が、図2-1で選んだ四角に塗られ、その下に選んだ色の名前が表示される。また、純色ではない色(トーン)を使いたいときには、内側の円から色を選んでクリックするとその色のトーン表(図2-3)が出るので、純色の場合と同様そこから使いたい色を選んでクリックすると、その色が図2-1で選んだ四角に塗られ、その下に選んだ色の名前が表示される。 図2-1の全ての四角について色を塗り、配色が完成したら、確認ボタンをクリックすると、正解・不正解がわかり、正解の場合は次へ進むボタンが出、不正解の場合はフィードバックして学習し直すことが出来るようになっている。
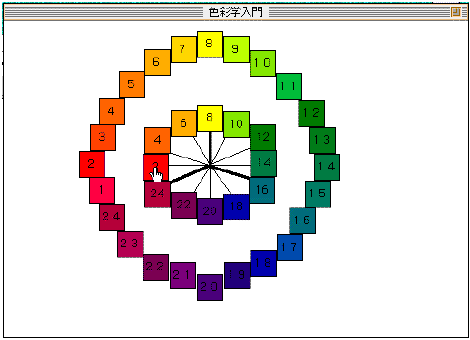
図2-2色相環
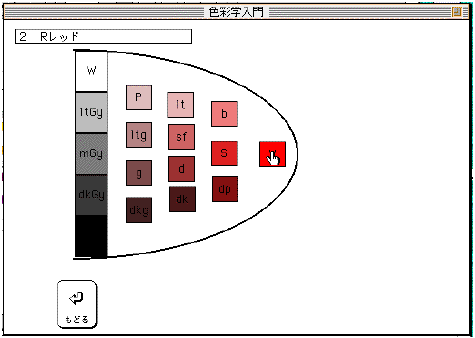
図2-3トーン表
ソフト開発には、MacintoshのHyperCardとColorizing HyperCard1.0を使用し、プロジェクトチームの倉持氏(情報科学専攻)の協力を得た。
開発する上で一番問題となったのは、どれだけ正確に色を表現できるかということである。本来なら、基本のRGBをもとに計算によって色を求めればよいのだが、Macintoshのモニター画面 における純色の緑と今回使用する(財)日本色彩研究所が定めたカラーシステムにおける純色の緑とが明らかに違っていたのでそれが出来なかった。よって、ここでは見ためをより日本色彩研究所が定めた緑に近づけるため、純色の緑の明度を半分にして計算した。
そのため、当初は問題の正誤の判断を、色相、明度、彩度の値や、RGBの割合の変化によって行おうと考えていたが、不可能になった。したがって、正誤の判断は、色を塗ったときに表示される色の名前を文字部分と数字部分に分け、その変化によって判断することにした。
現段階においては、不本意ながら設計と開発のみで終わってしまっているが、 今後の課題として、評価実験が必要性があげられる。 その対象者、方法等を以下に示す。
対象者は大学生とし、各分野(全5章)から1〜2個づつ題材を選んで、本教材とプリント教材を別々の人に使用してもらい、学習効果の違いを調べる。評価実験用のアンケート、テスト、プリント教材を論文の資料として添付した。
参考文献
大島由里子(1993)『カラーコーディネーター1・2・3』明日香出版
大島由里子(1995)『ファッションコーディネート色彩能力検定』明日香出版