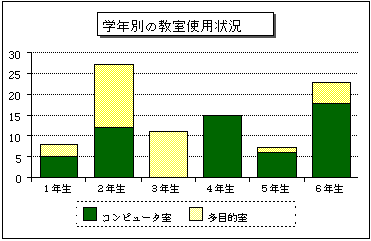 図1 学年別の教室使用状況
図1 学年別の教室使用状況Looking into Computer Classes at an Elementary School:
Observation and Analysis using Qualitative and Quantitative Methods
9351112 魚老名 美香
鈴木克明先生指導
コンピュータの教育利用が始まってから10年が過ぎた。今日では、コンピュータは身近なものとなり、コンピュータを用いた授業やそれを対象とした研究も行われるようになった。
本研究では、ある小学校のコンピュータ教室で実際に行われた授業について質的・量的に観察・分析し、その特徴をまとめた。
コンピュータを用いた授業は、従来の一斉授業とは異なる特性をもっている。そのため、これまで見られなかったような変化が起きており(大谷、1995a)、そのような点を発見するためには、観察を行い、授業をありのままに、場面や状況とのかかわりの中で捉えること(大谷、1995b)が必要である。このような研究手法を質的研究法という。
これに対し、量的研究法は、仮説枠を設け、カテゴリー化された項目の中で問題を捉えようとするもの(大谷、1995b)であり、複数の授業間の比較が数量的に容易になされる(吉崎、1995)という特徴ももっている。
この2つの手法は、対立するものではない。むしろ、相補的なものである(稲垣・佐藤、1996)。そのため、両手法を併用した研究も多い(大谷、1995b)。
以上のことから、本研究では、まず、小学校で行われているコンピュータを用いた授業について質的に観察・分析し、次に、そこで得られた知見を量的に分析することによって、コンピュータを使った授業の特色をまとめた。
O小学校でのコンピュータを用いた授業を対象とした。
O小学校は、コンピュータを導入してから3年目である。県の情報教育の研究指定校(1995年より2年間)でもあり、教員全員でコンピュータを使った授業に取り組んでいる。コンピュータの設置状況は、コンピュータ室(4列配置)に22台(NEC pc9821)、多目的室(オープンスペース)に23台 (NEC pc9821 cb3)となっている。コンピュータの使い方は、先生方に任されており、カリキュラムには位置づけられていない。また、各クラス週に1回ずつコンピュータ室と多目的室の使用を割り当てられている。
研究期間は、1996年6月5日から12月17日までで、週に1、2回(計31回)訪問し、105(うち6つは行事など)の授業を観察した。観察した授業の学年別・教科別の教室使用状況は、図1、2の通りである。
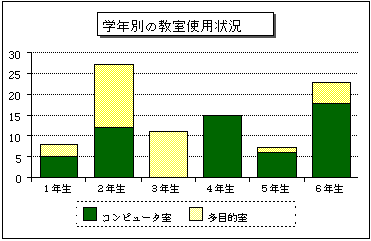 図1 学年別の教室使用状況
図1 学年別の教室使用状況
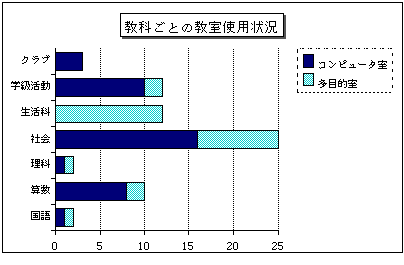 図2 教科別の教室使用状況
図2 教科別の教室使用状況
観察は、コンピュータ室や多目的室などの後ろに座ったり、先生や子どものそばに行って行い、手書きでメモをとり、それを授業ごとにコンピュータ上に記録した。そして、通し番号をふり、カード化した。
観察・記録を続け、データをまとめていくうちに、コンピュータを用いた授業の特色や、それぞれの授業の特色を決める要因だと思われることがらを30項目得た。次にそれらを10のカテゴリー(A〜J)に分け、ひとつひとつについてまとめた。その一部を記す。
<J 授業のやり方>
J-01 始めと終わりがはっきりしているか
コンピュータを使った授業では、先生が授業の始めと終わりに子どもを注目させて話をするものと、コンピュータ室に入ると同時に子どもがそれぞれ課題を始めるものがある。
事例1:皆が落ち着いたところで、「まず、10分間で地図をかいて」と椅子に座って説明する。パソコンを起動し始める。(中略)チャイムが鳴った。終了できたところもあるが、まだ途中のところもある。「みんなこっち向いて」ともとの椅子に戻って、「皆ボタン作れるようになったか、今度一人でボタン作れる人?」ときいたら、10人以上の手が挙がった。授業が終わって皆パソコンを終了させた。「ちゃんと終わらせたか、この画面が出たら終わっていいんだぞ」と声をかける。
事例2:男の子がフロッピーを配っている。エラーが出たり、「先生、もうやっていいの?」「前やったやつを出したい」と教室が雑然となる。先生が指示する間もなく、始まってしまったという感じ。先生は、子どもに引っぱられるようにしてあちこち回っている。それぞれがバラバラに始めているので、わからない子がたくさんいる。
事例1のように授業の始めと終わりがはっきりしている授業は、子どもに授業で何をやるのか、どこまでどのようにやればよいのか、ということが伝わっている。反対に、事例2のように曖昧である場合には、何をすればよいのかがわからず、課題に取り組むまでに時間がかかっている。
質的研究法によって得られた項目をひとつひとつの授業にあてはめ、得点(1-5)で表わした。そして、その頻度と相関を調べ、因子分析を行った。
因子分析の初期の結果として、表1に示す9つの因子が抽出された。因子の中の項目(例えば、A-01など)は、質的研究によって得たものである。9因子の中で、Factor 4までが、コンピュータを使った授業を見る上での尺度になるものとして解釈が可能だった。
6.おわりに
質的な研究によって、ひとつひとつの授業をさまざまな観点から見ることができた。また、量的な分析をすることによって、複数の授業間の比較を行い、質的な知見の検討を行うことができた。
今後の課題としては、分析をもとに、先生にインタビューをし、検討することが考えられる。
表1 因子分析により抽出された因子(初期)
Factor 1 一人ひとりに応じた指導 (固有値=5.865) A-01 一人一人と話す時間 A-02 先生が子どもに声をかけるか A-03 先生が歩き回るか A-04 遅れている子をよく見ているか A-05 先生が子どもと一緒に取り組んでいるか A-06 わかったこと、できたことを先生と 共有できるか(ほめてもらえるか) Factor 2 自分のやり方で学習できる環境 (固有値=4.318) B-01 コンピュータに触れる時間 J-03 子どもだけで進めるか J-04 子どもが自由にやれる時間があるか J-07 子どもが自分のペースで進めるか Factor 3 楽しめる授業 (固有値=3.619) ▲B-03 いらいらしたり、わからないままでいる ことがあるか C-01 先生が得意か苦手か C-02 先生も楽しんでいるか J-02 授業でやることが子どもにはっきり 伝わっているか Factor 4 ほかの人と共有する(固有値=2.114) ▲B-02 コンピュータに触れる子どもの数 D-01 子ども同士で話す(教え合う)か D-02 わかったこと、できたことを友だちと 共有できるか G-01 1人1台か2人1組かグループか H-04 教室の外の人とのやりとりがあるか Factor 5 (固有値=1.993) ▲F-01 全体に活気があるか H-03 コンピュータ以外にも道具があるか Factor 6 (固有値=1.515) ▲A-07 子どもの質問に答えているか E-01 先生同士で話すことがあるか Factor 7 教師の力量(固有値=1.268) J-01 始めと終わりがはっきりしているか J-05 先生の話を子どもがきいているか Factor 8 コンピュータの操作(M=1.112) I-01 操作のやり方に使われる時間 Factor 9 学年 (固有値=1.019) ▲G-02 子どもが動き回るか H-02 コンピュータに慣れるためか道具として 使うか
注:▲は、負の相関を示す。
参考文献
稲垣忠彦、佐藤学 1996「授業研究入門」岩波書店
大谷尚 1995 「コンピュータを用いた授業を対象とする質的研究の試み」 日本教育工学雑誌18(3/4)Pp.189-197
大谷尚 1995 「質的アプローチが教育工学において目指すもの」 日本教育工学会第11回講演論文集, Pp.11-14
吉崎静夫 1995 「授業研究法としての定量的アプローチ」 日本教育工学会第11回講演論文集,Pp.7-10