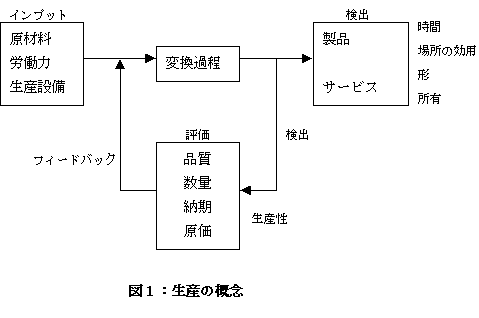←講義のツボメニューへ
←統合情報システム学TOPへ 統合情報システム学
【2002.6.25】【第21回】生産活動・管理と情報システム
生産活動
・昔・・・コストを抑えず商品を作り、値段を決め買える人だけ買わせる形
・現在・・・売値がほぼ決まっており、それに合わせてコストを抑えて造る
生産システム
生産をシステムとして考えた場合、次のように原材料、生産設備、労働力のインプットから
製品、サービスをアウトプットする1つの変換過程と考えられる
・原材料、生産設備、労働力などの生産要素から構成されている
・インプットを投入し、変換を行い、アウトプットを産出する
・それ自体が独自に活動するのではなく、他の諸活動と関わりをもち、作用しながら活動している
図1の各評価要素についての生産管理の機能は次のものである
・製品と品質の視点から
社会や市場の要求を調査し、これを満たす製品の使用を具体化し、
それを生産し提供すると共に、その品質を保証する機能
・数量と納期の視点から
社会や市場が要望する時期に、必要とする量を生産し提供する機能
・価格(原価)の視点から
社会や市場が要望する価格で提供し得る減価で生産する機能
生産管理の諸活動をマネジメントサイクルのもとに体系付けた場合、
『生産計画(計画)』『生産統制(実施)』『差異分析(統制)』という基本プロセスに大別される。
その概念は以下のものである
・生産計画
機械設備、原材料・部品、労働力といった生産活動における構成要素を製品やサービスとしての産出物へ変換するため、"何を、いつ、どこで、どの量を作るか"を決定するとともに、"どのようにしたら最も経済的に作れるか"について決定する
・生産統制
立案された生産計画を維持しさらに改善するため、生産活動の実績を適切な場所で適切な時点に適切な方法で測定し、計画内容との対比による評価を行い生産活動に対する的確な措置を指示する。
・差異分析
生産された製品について、生産計画において設定されたいくつかの評価の視点から計画と実績についての対比・分析を行う。差異があった場合はその原因を分析し、次の生産計画に反映させる。