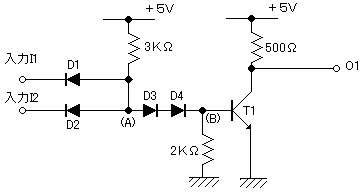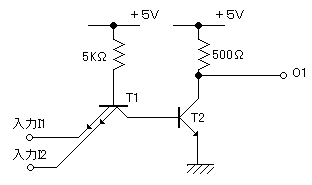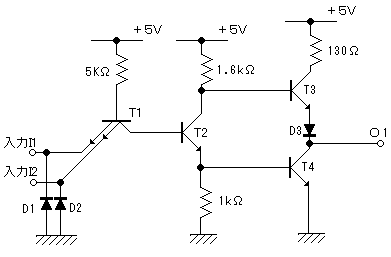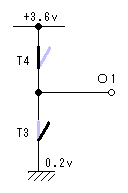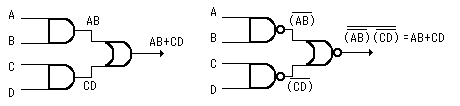5.1図にダイオード2個を用いた2入力ANDゲート回路を示す。
2.1で電気回路はいつも電流が還流するものであり、ループになって閉じた配線になっていると 説明した。4.2図5.1図などでは回路と言っていながらこの原則にマッチした図にはなっていない。 それには2つ理由がある。1つは電源の配線とアースとを部分的記号で示すだけで完全な配線を 書いてはいない。これは全部書くと図が煩雑になるため常識的に判ることとして省略してある。 2つめは入力より前段の回路部分、出力の公団の次の回路部分を省略して書いていない。 これは描くときりが無く次へ次へとつながるので図がまとまらなくなる。よって省略することが 普通である。
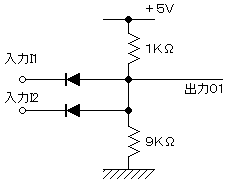
図5.1 ダイオードによる2AND
この図で、I1またはI2が電位0vならばO1 の電位は0.7vになる。(0.7vはダイオード順電位)
I1およびI2両方が電位5vならば、O1 の電位は4.5vになる。(オームの法則による)
もし電位0.0〜1.0vの範囲を論理記号”0”、電位2.0〜5.0vの範囲を論理記号 ”1”として弁別するならば、この回路は2入力ANDゲートとして働く。トランジスタは 使用しなくても、2ANDが実現するかに見える。しかしこの回路は5.2図のように 複数段を縦接続すると上手くいかない。
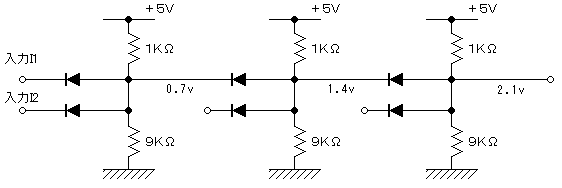
図5.2 ダイオードANDゲートの3段縦属接続
上図のように1段ごとにダイオード順電圧0.7vが累積していくから、3段目の 出力が2.1vになる。本来は0v論理”0”であってほしいところが2.1では 論理上”1”に弁別されてしまう。