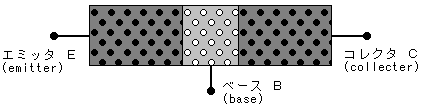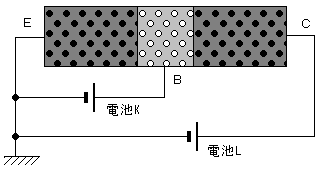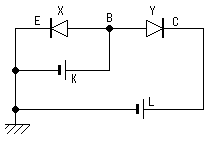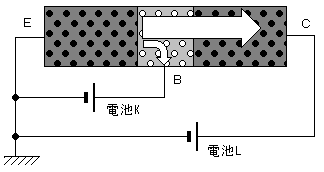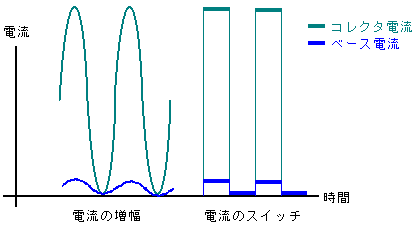僴乕僪僂僃傾婎慴
2002擭搙斉僥僉僗僩
俁丏僩儔儞僕僗僞
3.1.僩儔儞僕僗僞偲偼
僩儔儞僕僗僞偼俀侽悽婭傪戙昞偡傞敪柧偺價僢僌3偺堦偮偵擖傞丅僔儑僢僋儗僀懠俀柤
偺敪柧幰偼僲乕儀儖徿傪庴徿偟偰偍傝丄尰戙偺暥柧傪宍惉偡傞婎杮梫慺偺堦偮偵側偭偰偄傞丅
3.2.敿摫懱偲偼
揹婥偺椙摫懱乮嬥丄嬧丄摵丄傾儖儈摍乯偱傕側偔丄愨墢懱乮僑儉丄摡婍摍乯偱傕側偔丄揹埑傗
嬐偐側晄弮暔偵傛偭偰丄偁傞掱搙偺揹棳偑棳傟傞傕偺傪敿摫懱偲偄偆丅僔儕僐儞乮宂慺乯偑
偦偺揟宆揑側椺偱偁傞丅尦慺偺廃婜棩昞偱嘩懓偺傕偺乮懠偵扽慺丄僎儖儅僯僂儉側偳乯偑奨摂
偡傞丅嘩懓偼嵟奜廃偺揹巕偑係屄偺傕偺偱偁傞丅乮嵟奜廃偺揹巕偺屄悢偑懓偵懳墳偡傞丅乯
僔儕僐儞寢徎偺尨巕偺暲傃曽傪3.1恾偵帵偡丅偙偺応崌偼椬摨巑偺揹巕傪嫟桳偟偁偭偰丄尒偐偗忋
嵟奜廃偺揹巕偑俉屄偲側偭偰偄傞丅
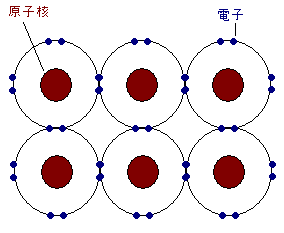 恾3.1 僔儕僐儞寢徎偱偺尨巕偺暲傃曽偲嵟奜廃偺揹巕偺忬嫷
恾3.1 僔儕僐儞寢徎偱偺尨巕偺暲傃曽偲嵟奜廃偺揹巕偺忬嫷
俉屄偼埨掕忬懺側偺偱丄嵟奜廃偺揹巕偺嬍撍偒徴撍偼敪惗偟偵偔偄丅偩偐傜偙偺傑傑偱偼丄
僔儕僐儞偼偐側傝愨墢暔偵嬤偄丅
3.3.値宆敿摫懱
僔儕僐儞偵嘪懓偺尦慺偱偁傞儕儞傪旝検偵崿擖偡傞丅嘪懓偼丄嘩懓偺僔儕僐儞偵尨巕峔憿偑帡偰偄傞偺偱丄
寢徎偺拞偵擖傝崬傫偱埨掕偵寢崌偡傞偑丄儕儞偺尨巕偼嵟奜廃偺揹巕偑俆屄側偺偱丄侾屄梋偭偰偄傞丅偙偺
梋偭偰偄傞揹巕偼寢崌偡傞憡庤偑側偄偺偱丄嬐偐側僄僱儖僊乕偱懇敍傪敳偗弌偟偰帺桼揹巕偵側傝偆傞丅
偡側傢偪丄揹巕偺嬍撍偒徴撍傪婲偙偟傗偡偄峔憿偵側偭偰偄傞丅偙傟偼摵偵晹暘揑偵帡偨峔憿偱偁傝丄
椙摫懱偵嬤偄惈幙偲側傞丅偙偺傛偆側敿摫懱傪値宆敿摫懱乮Negatice Carrier 敿摫懱乯偲屇傃丄
偦偺峔憿傪3.2恾偵帵偡丅
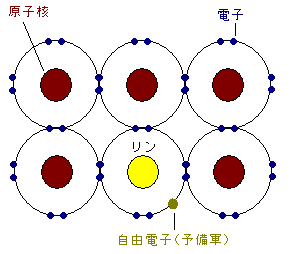 恾3.2 儕儞偑崿擖偟偨値宆敿摫懱偺嵟奜廃偺揹巕偺忬嫷
恾3.2 儕儞偑崿擖偟偨値宆敿摫懱偺嵟奜廃偺揹巕偺忬嫷
3.4.俹宆敿摫懱
僔儕僐儞偵嘨懓偺尦慺乽僈儕僂儉乿傪旝検偵崿擖偡傞丅嘨懓偼嵟奜廃揹巕偑俁屄偱偁傞偑丄嘩懓偲峔憿偑
嬤偄偺偱丄埨掕偵寢崌偡傞丅偟偐偟僈儕僂儉尦慺偺偲偙傠偼埨掕側揹巕偺屄悢偵偼侾屄懌傝側偄忬懺側偺偱丄
嬤椬偵帺桼揹巕偑偁傟偽懆偊偰偟傑偆懱惂偵偁傞丅3.3恾嶲徠丅
揹巕乮儅僀僫僗揹壸乯傪棊偲偟寠偺傛偆偵曔傜偊偰偟傑偆丄偲偺僀儊乕僕偐傜丄Positive Hole 丗乽惓岴乿
偲傕屇偽傟傞丅幚嵺偺棊偲偟寠偩偲偄偭偨傫棊偪傞偲敳偗傜傟側偄偑丄僈儕僂儉尨巕偺奜廃偵擖偭偨揹巕偺
懇敍椡偼偦傟傎偳嫮偔偼柍偄丅側偤側傜杮棃偺揹巕偺屄悢乮俁屄乯傛傝傕丄侾屄懡偔側傞偐傜丄揹婥揑偵偼
儅僀僫僗揹壸傪懷傃傞丅傛偭偰揹埑偺塭嬁偑媦傇偲偦偺椡傪庴偗偰偦偺曽岦偺暿偺惓岴傊堷偒婑偣傜傟偰
梕堈偵堏傞偐傜偱偁傞丅偩偐傜棊偲偟寠傛傝偼乽嬻偒嵗惾乿偺傛偆側僀儊乕僕偱偁傞丅乮僈儕僂儉尨巕僆儕
僕僫儖偺惓岴偼惓偺揹壸傪傕偮傢偗偱偼側偄丅偟偐偟偙偺僆儕僕僫儖側惓岴偑偨傑偨傑嬤椬偺僔儕僐儞偺揹
巕傪扗偆偲丄惓岴偑僔儕僐儞偺曽傊堏摦偟偨偐偺寢壥偲側傞丅偙偺傛偆偵擇師揑偵嬤椬偵敪惗偟偨惓岴偼丄
杮棃偺揹巕偑扗傢傟偰偄傞偺偱惓偺揹壸傪懷傃傞丅偙偺帪僈儕僂儉偱偼杮棃傛傝揹巕偑侾屄懡偄偺偱丄
晧偺揹壸傪傕偮丅乯
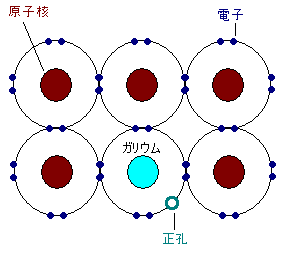 恾3.3 僈儕僂儉偑崿擖偟偨俹宆敿摫懱
恾3.3 僈儕僂儉偑崿擖偟偨俹宆敿摫懱
偙偺傛偆側惓岴乮嬻偒嵗惾乯傪帩偭偨敿摫懱偺応崌偼丄偁傑偭偨奜廃揹巕偺嬍撍偒徴撍偑婲偙傞偺偱偼側偔丄
嬻偒嵗惾偵桿堷偝傟偰旘傃搉傞傛偆側忬嫷偱揹巕偺堏摦乮媡曽岦傊偺揹棳偺堏摦乯偑偍偙傞丅寢壥揑偵偙傟傕
堦庬偺摫懱偱偁傝丄偙傟傪俹宆敿摫懱乮Positive carrier乯偲屇傇丅
3.4.倫値愙崌
3.4恾偵帵偡傛偆偵丄偁傞堦懱偺僔儕僐儞寢徎偺敿暘傪倫宆敿摫懱丄巆傞敿暘傪値宆敿摫懱偲偡傞丅
恾偱偼崟娵傪帺桼揹巕丄敀娵傪惓岴偲偟偰偄傞丅
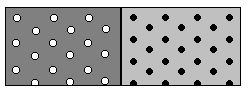 恾3.4 倫値愙崌
恾3.4 倫値愙崌
倫値愙崌偺嫬奅傪愙崌柺偲尵偆丅乮暿乆偵嶌偭偨2屄偺寢徎傪墴偟晅偗偰傕愙崌偵偼側傜側偄丅
嫬奅偵嬻婥傗巁壔枌偑夘嵼偟丄尨巕儗儀儖偱偺枾拝柺偵偼側傜側偄丅幚嵺偺倫値愙崌偼堦懱偺
曣懱偲側傞僔儕僐儞寢徎偵嬫堟傪暘偗偰丄僀僆儞懪偪崬傒傗奼嶶側偳偺岺掱傪巤偟偰惢嶌偝傟傞丅乯
偙偺傛偆側摿庩側峔憿偺寢徎偱偼丄擬僄僱儖僊乕偵傛傞揹巕偺妶摦偵傛偭偰丄値宆椞堟偺儕儞偺
俆屄栚偺揹巕偑帺桼揹巕偵側偭偰愙崌柺傪挻偊偰倫椞堟偺僈儕僂儉偺嬻偒嵗惾偵擖傝崬傓丅
寢壥偲偟偰愙崌柺偺椉懁偺堦掕偺嬫堟偱恾3.5偺傛偆偵惓岴偲帺桼揹巕偑寢崌偟徚柵偟偰偟傑偆丅
徚柵偟偨椞堟傪嬻朢憌偲屇傇丅
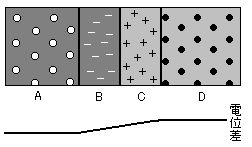 恾3.5 倫値愙崌柺偱敪惗偡傞嬻朢憌偲懷揹
恾3.5 倫値愙崌柺偱敪惗偡傞嬻朢憌偲懷揹
値宆偺椞堟俠偺儕儞尨巕偐傜椞堟俛傊帺桼揹巕偑奼嶶偡傞偲丄巆偭偨儕儞尨巕偼揹巕偑侾屄
彮側偔側傞暘偩偗僾儔僗偵懷揹偡傞丅倫宆椞堟偺俛偺僈儕僂儉尨巕偺惓岴偵帺桼揹巕偑侾屄
曗懌偝傟傞偲丄揹巕偑侾屄梋寁側暘偩偗儅僀僫僗偵懷揹偡傞丅偙偺寢壥3.5恾偺傛偆偵俛椞堟
俠椞堟偵懷揹偑婲偙傝丄俛俠娫偵揹埵嵎兂乮栺0.7V乯偑敪惗偡傞丅D椞堟偵巆偭偰偄傞帺桼揹巕
偑俠,俛傪捠傝墇偟偰俙椞堟傑偱摓払偟偰惓岴偵曔懆偝傟傞偲丄懷揹検偑奼戝偡傞丅偟偐偟俢偺
帺桼揹巕偑擬奼嶶偟傛偆偲偡傞椡偲丄俛俠娫偵揹埵嵎兂偑偁傞偨傔丄揹壔偼嶶堩偣偢丄偍屳偄偵
愙崌柺偵堷偒婑偣傜傟丄堦掕偺暆偺嬻朢憌偑堐帩偝傟傞丅
3.5恾偺傛偆偵丄倫値愙崌柺偱懷揹偑敪惗偡傞尰徾偼杸嶤偵傛傞惓揳懷揹偲椶帡偟偰偄傞偐偵尒偊傞丅
偟偐偟杸嶤偺応崌偼奜晹偐傜杸嶤僄僱儖僊乕傪壛偊偨寢壥偺懷揹偱偁傞丄杸嶤傪拞巭偡傞偲丄
惷揹婥偼偄偢傟曻揹偟偰偟傑偆丅倫値愙崌偺応崌偼奜晹偐傜摿暿側僄僱儖僊乕偼庴偗偢偵丄
忢壏偺擬僄僱儖僊乕偲帠屘偺摿庩側尨巕峔憿偵婲場偡傞撪敪揑側懷揹偱偁傝丄帪娫偑偨偭偰傕
徚柵偟側偄丅偨偩偟懷揹偟偰偄傞僾儔僗偲儅僀僫僗偲偼摨検偱偁傝丄奜偐傜慡懱傪傂偲偮偲偟偰尒傞偲
僩乕僞儖懷揹検偼僛儘偵側偭偰偄傞丅
3.5.倫値愙崌僟僀僆乕僪
倫値愙崌偵懳偟偰3.6乛3.7恾偱偟傔偡傛偆偵揹埑倁偺揹抮傪偮側偖丅揹抮偺揹埑偺曽岦偼兂傪
懪偪徚偡曽岦偱丄俢偺椞堟偐傜帺桼揹巕傪俙偺曽岦傊墴偟弌偡曽岦偱偁傞丅偟偐偟丄倁亙兂偺
応崌偼丄俛俠椞堟偐傜庴偗傞斀敪椡偺傎偆偑嫮偄偺偱丄帺桼揹巕偺俢仺俙傊偺堏摦偼旝検偩偑丄
倁亜兂偵側傞偲丄揹抮偺揹埑偑斀敪椡傪忋夞傝丄偦偺揹埑偺屻墴偟偱帺桼揹巕偼偳傫偳傫
俢仺俙偺堏摦傪奐巒偡傞丅
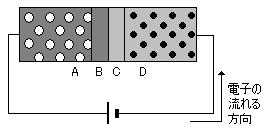 恾3.6 揹抮偺愙懕
恾3.6 揹抮偺愙懕
偙偺応崌偼3.5恾偺傛偆側屒棫偟偨慺巕偱偼側偔丄揹婥夞楬偑宍惉偝傟偰揹抮偐傜帺桼揹巕偑偄偔傜
偱傕嫙媼乛媧堷偝傟傞偺偱丄怤擖偟偨帺桼揹巕偑丄俙椞堟偱拁愊偡傞偙偲偑側偔丄夞楬慡懱傪娨棳偡傞丅
偙偺忬懺偵側傞偲俙椞堟偺惓岴乮嵗惾乯丄俢椞堟偺帺桼揹巕梊旛孯丄偲傕偵揹棳偑捠夁偡傞偩偗偺
枾搙偑偁傞偺偱丄摵傎偳偱偼側偄偵偟傠丄廫暘僗儉乕僘偵揹棳偑棳傟傞丅揹抮偺揹埑倁傪倁亖侽偐傜
偩傫偩傫抣傪戝偒偔偟偨偲偒偵揹棳偑棳傟傞忬嫷傪僌儔僼偵彂偔偲丄師偺傛偆偵側傞丅
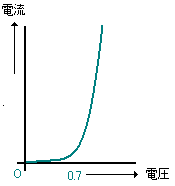 恾3.8 揹抮偺揹埑倁傪曄偊偨帪偺揹棳
恾3.8 揹抮偺揹埑倁傪曄偊偨帪偺揹棳
師偵3.9恾偵帵偡傛偆偵揹抮偺柍婡傪斀懳偵偟偰倫値愙崌偵愙懕偡傞丅
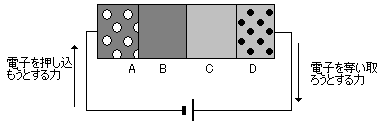 恾3.9 揹抮傪媡岦偒偵愙懕
恾3.9 揹抮傪媡岦偒偵愙懕
偡傞偲俙椞堟傊偼揹抮偐傜帺桼揹巕偑憲傝崬傑傟傞偺偱丄惓岴乮嵗惾乯偵曔懆偝傟偰俛椞堟偑奼戝
偡傞寢壥偲側傞丅懠曽俢椞堟偱偼丄揹抮偑帺桼揹巕傪偆偽偄偲傞偺偱丄俠椞堟偑奼戝偡傞寢壥偲側傞丅
俛椞堟偱偼揹巕傪曔懆偟偨暘偩偗儅僀僫僗懷揹偑憹戝偡傞丅俛椞堟偺惓岴偵嵶偔偝傟偰偄傞揹巕偼丄
儅僀僫僗懷揹偺揹婥揑埑椡偑嫮傑傝丄俙椞堟傊怤擖偟傛偆偲偡傞揹巕傪偼偹偐偊偡丅傑偨帺桼揹巕傪
幐偭偨俠椞堟偑奼戝偟偰偄傞偨傔丄嬍撍偒徴撍傪偟偰俢倛倕敳偗弌傞偙偲偑偱偒偢偵俛偵懾棷偟偰偟傑偆
丅揹抮偺偱傫偁偮倁傪戝偒偔偡傟偽偝傜偵俛,俠,偑奼戝偡傞丅
寢壥偲偟偰丄偙偺曽岦偵揹抮傪愙懕偡傞偲丄倁傪戝偒偔偟偰傕揹棳偼棳傟側偄丅
3,7恾偺岦偒偺揹埑傪惓曽岦丄3,9恾偺岦偒傪晄曽岦偲偟偰丄椉曽傪偁傢偣偰揹埑丗揹棳偺
僌儔僼傪彂偔偲丄3,10恾偺懢慄偺傛偆偵側傞丅乮揹抮偵晛捠偺掞峈傪愙懕偟偨偲偒偺揹棳偼
揰慄乯
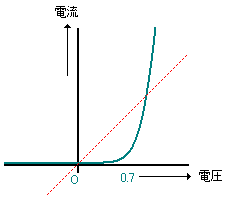 恾3.10 倫値愙崌僟僀僆乕僪偺揹埑乛揹棳丂摿惈
恾3.10 倫値愙崌僟僀僆乕僪偺揹埑乛揹棳丂摿惈
偙偺傛偆偵堦曽岦偺傒揹棳傪傛偔捠偟丄媡曽岦偵偼戝偒側揹埑偑偐偐偭偰傕揹棳傪捠偝側偄
慺巕傪僟僀僆乕僪乮Diode乯偲屇傃丄夞楬婰崋偼  偱偁傜傢偡丅
偱偁傜傢偡丅
3.6.僩儔儞僕僗僞乮僶僀億乕儔宆乯
3,11恾偵値宆敿摫懱偺娫偵倫宆敿摫懱傪偼偝傫偱僒儞僪僀僢僠峔憿偵偟偨値倫値僩儔儞僕僗僞傪帵偡丅
乮摨條偵倫値倫僩儔儞僕僗僞傕偁傞乯
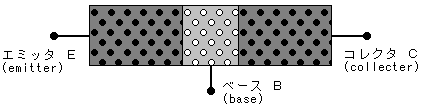 恾3.11 値倫値僩儔儞僕僗僞
恾3.11 値倫値僩儔儞僕僗僞
偙偺峔憿偵摓払偡傞傑偱偵婔懡偺帋峴嶖岆傗岾塣偺恻梋嬋愜傪宱偰偄傞丅幚嵺偺僩儔儞僕僗僞偱偼
儀乕僗偺岤傒偑旕忢偵敄偔弌棃偰偄傞偑丄恾帵偡傞搒崌忋偐傜暘岤偔昤偄偰偄傞丅
偙偺僩儔儞僕僗僞偵3,12恾偺傛偆偵揹抮傪愙懕偡傞丅
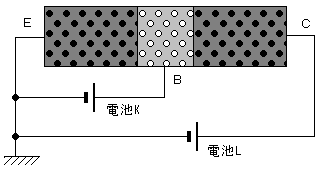 恾3.12 値倫値僩儔儞僕僗僞
恾3.12 値倫値僩儔儞僕僗僞
愙崌倃偵懳偡傞揹抮俲偺娭學偼3,7恾偲摨偠曽岦偱偁傝丄偙偺夞楬乮揹抮俲仺俛仺倃仺俤仺揹抮俲乯
偱偼丄揹埑偑侽丏俈倁埲忋側傜揹棳偑僟僀僆乕僪偺弴曽岦偺摿惈偵増偭偰棳傟傞丅
堦曽揹抮俴偐傜弌敪偟偰娨棳偡傞夞楬乮俴仺倄仺俛仺倃仺俤仺俴乯偼丄愙崌倄偱偼僟僀僆乕僪媡曽岦
丄愙崌倃偱偼僟僀僆乕僪弴曽岦丄偲宱桼偡傞丅偙偺忬嫷傪僟僀僆乕僪婰崋傪梡偄偰夞楬恾偵偡傞偲3.13
恾偲側傞丅
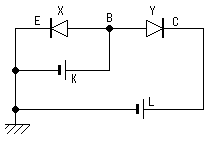 恾3.13 僟僀僆乕僪偵抲姺偟偨夞楬
恾3.13 僟僀僆乕僪偵抲姺偟偨夞楬
偙偺夞楬傪扨弮偵夝庍偡傞偲揹抮俲傪娨棳偡傞夞楬偱偼揹棳偑僗儉乕僗偵棳傟傞偑丄揹抮俴偺
夞楬偱偼丄僟僀僆乕僪偑侾屄媡曽岦偵擖傞偺偱揹棳偼棳傟側偄丅
偙偙偱丄幚嵺偺僩儔儞僕僗僞偺儈僜偼丄3,12恾偺僒儞僪僀僢僠偺傑傫拞偺儀乕僗椞堟傪旕忢偵敄偔
惢嶌偡傞偙偲偵偁傞丅乮侾儈僋儘儞埲壓乯偡傞偲丄扨弮側3,13恾偺夞楬偱偼愢柧偱偒側偄尰徾偑
揹巕儗儀儖偱婲偙傞
傑偢俲傪娨棳偡傞夞楬傪揹巕偺儗儀儖偱峫偊傞丅3,12恾偵偍偄偰丄揹抮俲偺揹埑偺椡偱俲偺晧嬌
傪弌敪偟偨帺桼揹巕偑俤抂巕偐傜値宆敿摫懱椞堟傊怤擖偡傞丅俲偺揹埑乮揹埵嵎乯偑侽丏俈倁傪
廫暘偵忋夞偭偰偄傞応崌偼帺桼揹巕偼愙崌倃偺忈暻揹埑乮侽丏俈倁乯傪忔傝墇偊偰倫宆椞堟乮亖儀乕僗
椞堟乯傊摓払偡傞丅偙偙偱偼俛抂巕偑愙懕偝傟偰偄偰揹抮俲偺惓嬌偑帺桼揹巕傪偳傫偳傫扗偄庢傞偐傜
帺桼揹巕偼夞楬傪堦弰偡傞丅
偙偙偱丄儀乕僗椞堟偑旕忢偵敄偔嶌傜傟偰偄傞偲丄儀乕僗椞堟傊怤擖偟偨帺桼揹巕偑惓岴偵曗懌
偝傟丄偝傜偵俛抂巕偐傜奜傊扗傢傟傞堦曽偱丄愙崌倄偵傕摨帪偵摓拝偡傞丅乮検揑偵偼倄傊摓払
偡傞傕偺偺曽偑懡偄丅昞柺愊偑懡偄偐傜乯愙崌倄偺塃懁偺椞堟偼値宆敿摫懱偱偁傝丄3.6恾偵帵偡
傛偆偵丄塃偐傜嵍傊岦偐偆揹巕偼揹埵忈暻偵挼偹曉偝傟傞偑丄嵍偐傜塃傊岦偐偆揹巕側傜偽
揹埵嵎偵堷偒婑偣傜傟傞丅偄傑儀乕僗椞堟偱弌岥抂巕俛傊峴偔慜偵偁傆傟偰愙崌倄偵嬤婑偭偨揹巕偼
偙偺堷偒婑偣岠壥偵傛偭偰偳傫偳傫値宆敿摫懱亖俠椞堟傊媧偄弌偝傟傞丅偡傞偲俠抂巕偵偼揹抮偺俴偺惓嬌
偑愙懕偝傟偰俠椞堟偺揹巕傪偳傫偳傫扗偄庢傞丅寢壥偲偟偰揹抮俴偺夞楬偵傕揹棳偑娨棳偡傞丅
乮俴扨撈夞楬偱偼愙崌倄偑媡嬌惈偺偨傔偵揹棳偼棳傟側偄偑丄俲夞楬偺彆偗傪庁傝偰媡懏惈偵墶寠
傪偁偗傞傛偆偵偟偰棳傟傞乯偙偺忬嫷傪3.14恾偵帵偡丅
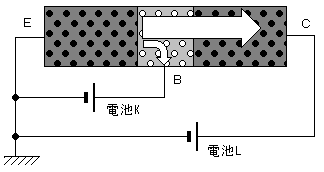 恾3.14 俲夞楬乮儀乕僗夞楬乯偲俴夞楬乮僐儗僋僞夞楬乯偵棳傟傞帺桼揹巕偺棳傟
恾3.14 俲夞楬乮儀乕僗夞楬乯偲俴夞楬乮僐儗僋僞夞楬乯偵棳傟傞帺桼揹巕偺棳傟
俴夞楬偵棳傟傞揹棳偼丄俲夞楬偺彆偗傪庁傝偰棳傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺検偼俲偺俀侽攞掱搙
偵側傞丅偦偺棟桼偼丄儀乕僗椞堟偑旕忢偵敄偔弌棃偰偄傞偐傜偱偁傞丅儀乕僗偵怤擖偟偨帺桼揹巕偼
儀乕僗抂巕弌岥傊摓拝偡傞傛傝傕愭偵丄戝懡悢偼愙崌倄偵嬤婑傝丄僐儗僋僞椞堟偵偐偐偭偰偄傞崅偄揹埑
俴偵媧偄弌偝傟偰僐儗僋僞椞堟傊擖傞丅擖偭偨揹巕偼偦偺傑傑揹埑俴偵堷偭挘傜傟偰僐儗僋僞抂巕弌岥傊
岦偐偆丅
偙偙偱揹抮俲偺揹埑俲偑彮偟曄壔偟丄偦偺寢壥俤仺俛傊偺揹巕偺棳傟乮俛仺俤傊偺揹棳乯偺検偑丄
傾僫儘僌揑偵侾丆俀丆俁偲曄壔偡傞偲丄俤仺俠傊偺揹巕偺棳傟乮俤仺俠傊偺揹棳乯偼俀侽丆係侽丆俇侽
偲曄壔偡傞丅偙偺尰徾傪憹暆偲屇傇丅乮憹暆棪俀侽攞乯
俤仺俛傊偺揹巕偺棳傟偺検偑丄僨僕僞儖揑偵侽丆侾偲曄壔偡傞偲丄俤仺俠傊偺揹巕偺棳傟偼侽丆俀侽偲
曄壔偡傞丅偙偺尰徾傪幷抐偲偐僗僀僢僠偲屇傇丅乮椉曽偲傕杮幙揑偵偼摨偠尰徾乯
慜幰偺憹暆摦嶌偼僥儗價丄儔僕僇僙丄実懷揹榖側偳偱丄旝庛側怣崋偼寁傪奼戝偡傞偨傔偵棙梡偝傟傞丅
屻幰偺僗僀僢僠摦嶌偼僐儞僺儏乕僞偦偺懠僨僕僞儖婡婍偱侾屄偺摦嶌傪値屄傊揱偊傞偨傔丄偍傛傃
僼儕僢僾僼儘僢僾夞楬偵墳梡偝傟偰忣曬傪婰壇偡傞偨傔偵棙梡偝傟傞丅
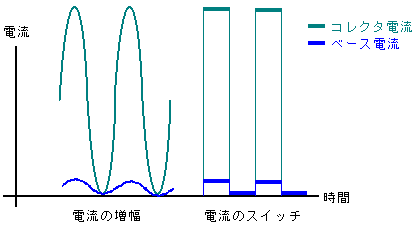 恾3.15
恾3.15
偙偺傛偆側憹暆傗僗僀僢僠偺摦嶌偼丄侾俋俆侽擭戙傑偱偼恀嬻娗偁傞偄偼儕儗乕乮僗僀僢僠偺傒乯
偱幚尰偝傟偰偄偨偑丄僩儔儞僕僗僞偼偦傟傜偵偼柍偄師偺摿挜傪傕偭偰偄傞丅
| 丒旕忢偵彫偝側儌僲偲偟偰幚尰偱偒傞丅 |
乮傕偲傕偲偑尨巕儗儀儖偺尰徾偱偁傞偐傜彫偝偔偰廫暘乯 |
| 丒旕忢偵崅懍摦嶌偑偱偒傞丅 |
乮傕偲傕偲偑揹巕偺堏摦偱偁傞偐傜憗偄乯 |
| 丒旕忢偵怣棅惈偺崅偄傕偺偲偟偰幚尰偱偒傞丅 |
乮堦懱偺屌懱偲偟偰偱偒偰偄偰丄徚栒偡傞晹暘側偟乯 |
| 丒戝検惗嶻偑壜擻偱偁傞丅 |
乮尨嵽椏僔儕僐儞偼柍恠憼偵嬤偄丅惗惉丄幨恀惢斉丄僈僗奼嶶側偳帺摦壔偑壜擻乯 |
偙傟傜偺憤崌岠壥偲偟偰堦愇偺側偐偵1000枩屄埲忋偺僩儔儞僕僗僞傪帩偭偨挻俴俽俬偑岺嬈
惢昳偲偟偰幚尰偝傟傞偵帄傝丄偄傑傗嶻嬈偺僐儊偲傕屇偽傟偰偄傞丅
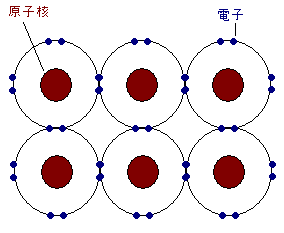
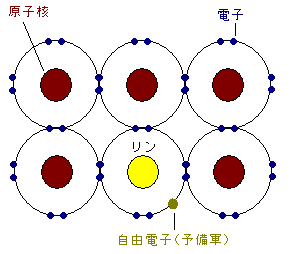
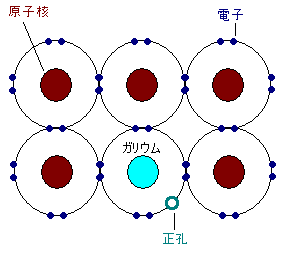
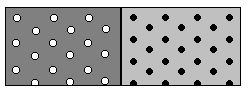
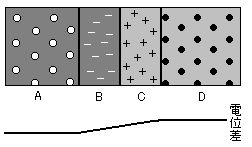
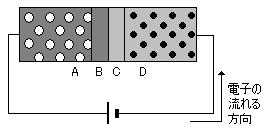
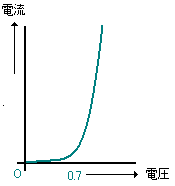
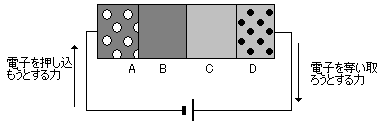
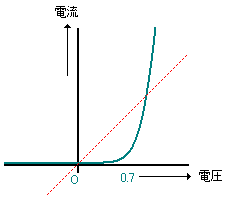
 偱偁傜傢偡丅
偱偁傜傢偡丅