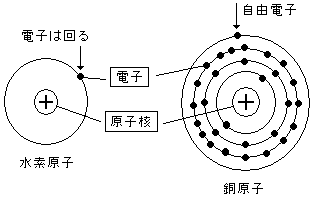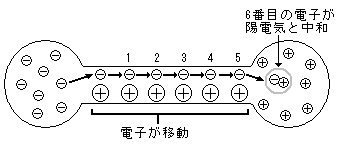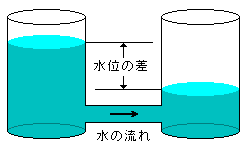ハードウェア基礎
2002年度版テキスト
1.電気とは何か
1.1.電気とは何か
われわれは日常から電気に囲まれて生活している。
しかし電気は目に見えないから、改まって電気とは何か?
と問われると簡単には説明できない。
電機は芽に見えないが、電機なるものが存在することは、
静電気摩擦現象や雷現象として太古から気づかれていた。
ここ200年ほどの間に、これらの現象の元が電気であり、
その本質は物質の中の電機の過剰・不足・移動、であることが
多くの実験と理論から分かってきた。
1.2.物質の原子構造
身の回りの物質は多くの素材が複合して形成されているが、
それらをどんどん細かい単位に分解すると、究極的には水素、炭素、窒素、
シリコン、鉄、アルミ、等の原始にまで行き着く。
原始は中心に原子核があり、その周りを複数個の電子が軌道を描いて
周回している。軌道には内側から2個、8個、18個、…、と電子が
入りうる座席がある。原子核の大きいもの(重いもの)ほど多くの
電子が周回している。最も軽い原子である水素原子では1個の電子がある。
銅の原子では、29個の電子があり、最も外側の4層目の軌道には1個の
電子がある。(図1.1)
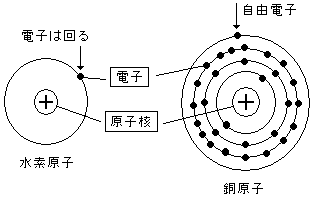 図1.1 原子の模型
図1.1 原子の模型
1個の原子は最小単位の電気量を帯びている。原子核の中には電子と逆の電気量を持つ
陽子があり、それぞれの原子核には周回する電子と同量の陽子があって、電気的には
バランスを保っている。陽子の方をプラスの電気、電子のほう
をマイナスの電気と定義している。
プラス電気とマイナス電気は互いに引き合う力があるので、電子は原子核の周囲に
力学的に集まっている。
1.3.電気の発生
普通に存在する物質では、上記のような状態にあり、電気的には何も無い中立バランス状態にある。
しかし、ある種の物質にある種のエネルギー(熱、磁力、科学、等)が加わると、
原子のまわりを周回する電子のうち最外周の束縛力の弱い電子がエネルギーを受けて束縛力を
振り切り、原子の外へ移動してしまう。
最外周の電子が1個抜けた原子はプラス電気を帯びる。抜けた電子は自由電子と呼ばれ、
マイナス電気を帯びる。
どういうエネルギーを与えると電気を発生できるか?それは宿主の物質によって異なる。
どうしても電気を発生し得ない物質も多い。最も身近に体験できるのは、
乾燥した雰囲気の中で化繊衣類を何か(人体とかプラスチックとか)と摩擦すると、
化繊の電子がプラスチック側に移動して、化繊が結果的にプラスに帯電する。プラスチック側
は、同量だけマイナスに帯電する。
また、強い磁力線が存在する中で銅対(銅線など)を磁力線を横断するようにある速度で動かすと、
胴体の一端に自由電子が集まりマイナスとなり、他端はプラスになる。(ただし動きを止めると
自由電子はすぐに導体中を動いてもとの場所へ戻ってしまう。)この現象は回転式発電機として応用されて、
われわれに日常生活に必要な電気を供給してくれている。
いずれの場合も或る条件でエネルギーを与えると、電気的にバランスしていた状態から、
プラスとマイナスに分かれた状態になる。ここでプラスとマイナスとは常に同量である。
宿主の物質自体は、電気的に中立バランスしている定常状態でも、プラスとマイナスとに
電気的な偏移を受けた状態(最外周電子が不足した状態や余剰な自由電子がある状態。)
でもその物質の力学的な構造や性質は何も変わらない。
1.4.電気の移動(電流)
発生した自由電子は真空中ならば本当に動き回れる。しかし普通は周囲は固体物質なので
周囲の原子に玉突き式にぶつかりながら移動する。移動がスムースに行われるかどうかは
周囲の原子構造、つまりは最外周の電子の個数に依存する。
図1.1で示す銅の原子の場合は、最外周に1個だけ電子がある。この電子は極めて小さな
エネルギーで原子の外へ飛び出せる。つまり銅の場合は、すべての原子が自由電子予備軍
を抱えており、どこか一端で外部からの自由電子が飛び込んでくると、すぐに玉突き現象
が発生して他端まで波及する。結果的に自由電子が極めてスムースに一端から他端へ通り
抜けたことになる。つまりは銅は電気の良導体である。この状況を図1.2に示す。
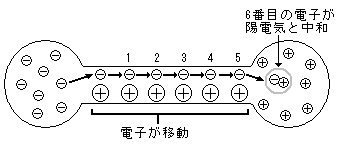 図1.2 銅の電線の中の電子の移動
図1.2 銅の電線の中の電子の移動
ある区間を電子が通り過ぎたとき、そこに電流が流れた、という。
(歴史的には、電流が先に観測されて、あとからそれが電子の通過である
ことがわかった。)図1.2では左から右へ電子が移動しているが、電子はマイナスなので、
マイナス電流が左から右へ流れたことになる。しかし電流はプラスで表現する週間なので、図1.2
では「電流が右から左に流れた」こととなる。
自由電子が発生はしても周囲の物質の原子構造が玉突きを許さない(自由電子予備軍が存在しない
)状態にあると、電子は移動できない。このような物質は電気の絶縁体であり、発生した
電子のマイナス電気はその場所に帯電することになる。(同量のプラス電気もいずこかに
帯電する。)マイナスにせよプラスにせよ同種の電気には反発力が働くので、あまりにも
多量の帯電が狭い区域に起こると反発力のために空気の層を通して近辺の良導体へ電子が
強引に移動する。これが放電である。
1.4.電流を流す力(電圧)
自由電子を作り出す力は、外部から与えられるある種のエネルギーに起因するが、結果として
発生した力は電子の移動すなわち電流となる。この電流を流す力を電圧という。
電圧と電流は、しばしば水に例えられて、水圧と水流に比較される。水の場合は
引力の影響によって高い位置(水位が高い)にある水が低い位置(水位が低い)にある水に
流れ落ちようとする。同じように電気の場合も高い電位の場所から低い電位の場所へ電流が流れる、
と表現し、2つの場所の電位の差を電位差という。
電圧と電位差は同義語である。図1.3に水位の例を示す。
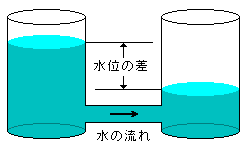 図1.3 水圧と水の流れ
図1.3 水圧と水の流れ
1.6.抵抗
銅は良導体である。(銀、金、アルミ、等も良導体)ゼロに近いわずかな電位差で大きな電流が
スムースに流れる。換言すると、電流が流れるときほとんど無駄なエネルギー消費が無い。
ゴム、陶器などは絶縁体であり、高い電圧がかかっても電流を通さない。電流が流れないから、
逆の意味でエネルギー消費も無い。
カーボン、タングステン、ニクロム線、等は導体ではあるが、電流が流れる佐井に発熱して、
エネルギーの消費が発生する。これらのエネルギー消費を伴う導体に電流を流すには、
それなりの電圧をかけてやらねばならない。電圧をかけても流れる電流の量はかなり制約される。
このような物質は電流を流す経路においてその量を適当に抑える働きをする素子として
活用できる。このような素子を「抵抗」という。(抵抗値は断面積に反比例
、長さに比例)