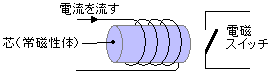今回の講義では、前回時間切れでできなかった「8.磁気メモリー」の最後の 部分の解説と演習を行いました。今回は演習の問題についての解答をアップ します。(磁気メモリーについては、第8回にまとめてアップします。)なお、 問題は授業中に提出してしまったので、大体の内容になります。解答も、模範解答が まだありませんので「当たらずとも中途半端に遠からず」的な解答になります。 間違ってもこの解答を丸写しすることだけは止めてください。 (間違っているかもしれませんが、あしからず。(^^;
第11回講義で模範解答をゲットしましたので、自分の解答と比較しつつアップします。
第3回課題解説?模範解答
問題1
SRFFの記憶機能について、動作表を用いて説明せよ。
S R Q1 Q2 備考 1 0 1 0 ”1”状態へセット 0 1 0 1 ”0”状態へリセット 0 0 前の状態 記憶続行 1 1 1 1 Q1=1、Q2=2は強制不安定状態で記憶続行はしない。
表6.1 SRフリップフロップ動作表
S入力R入力共に”0”のとき、SRFFは”1”状態にセット、 ”0”状態にリセットを行わず、以前の状態を保持する。
以下、解答を抜粋
「ある回路に記憶機能があるという場合の前提として、その回路が少なくとも2つの 安定状態(0状態と1状態)と持つことが必要である。そして、 「記憶機能がある」とは「時間が経過しても前の状態を維持する」ことである。 時間が経過するとの表現は言外に「書き込み入力が入来せずに時間が経過する」 との意味をこめている。換言すると「入力信号が存在しない時、前の状態を維持する」 ことである。すなわち動作表で言うと入力信号S、Rが両方とも0,0のとき、 出力がその前の状態を保持することである。(入力信号が存在する時でも、 クロックパルスが0の期間は、入力信号が存在しないのと同じで、状態を維持する。 これも1クロック期間限定の記憶と言える。
問題2
なんと、前回の解説で問題2を飛ばしてました。 慣れないことはするものではない。
DRAMでは、指定されなかった番地の記憶内容は指定された番地の記憶内容とは無関係にそのまま保持される。 それを実現している仕組みを説明せよ。 しかしながら番地指定されずに一定の時間が経過するとその番地の記憶内容が薄れるのは何故か。
模範解答
指定されていない番地では、ゲート電位0vのためMOSトランジスタスイッチがOFFとなり、 コンデンサの帯電電荷は他の回路から切り離されるため保持される。しかしLSIの内部では コンデンサと周囲との絶縁が完全ではないため僅かな電流が周囲へ流れ出し、 一定の時間が経過すると”1”の記憶内容の電位が低下して”0”と判別できなくなる。
また、これを未然に防止するのがリフレッシュである。
問題2問題3
磁石の磁界(磁極?)は粒子性の現象ではないことを説明せよ。
もし粒子性の現象だったら、両端に粒子が移動(両側から磁界が発生?)した時に、 真ん中から切断すれば、極性を分断することができるが、磁石ではそうならず、 真ん中から切断すると、切断面に新しく磁極が発生するから。
模範解答
磁石を途中で切断すると、切断した両側にN極とS極が出現する。 さらに細かく切断しても同様である。 もし最初のN極とS極の端の部分に何かが存在するとすれば切断した所には何も出現しないはずである。 いくら切断しても再現するのは磁石そのもの全体が本来こういう性質の物質でできていると考えるべきである。
問題3問題4
下の図は芯に常磁性体を使っているが、もし強磁性体を使ったらどうなるか?
常磁性体は磁界が消えると物質内の磁化も消えるため、スイッチのON/OFF を行うことができるが、強磁性体は、磁界が消えても物質内の磁化は残るので、 スイッチが入りっぱなしになってしまう。
模範解答
強磁性体は一端磁化すると外部の磁界がゼロになっても自身の直は残留する。 従って入力信号がゼロになっても残留直の磁力で接点を引っ張りつづけ、 スイッチはONになりつづける。(数年は持つ)
←トップへ
←授業選択画面に戻る
←鈴木研究室ホームへ