問題1
n型半導体のところどころにあるⅤ族原子リンは、外周の5番目の電子を放出しやすい。 放出する前の状態ではそのリン原子はプラスかマイナスかいずれかに帯電しているか?
解説
放出する前:帯電なし(リンは外周電子5個が本来の状態だから、無帯電である。) 放出した後:+帯電(なぜなら電子(-)が1個抜けたから、原子核の+が余剰となる。)
帯電の有無の基準は、その原子の本来の状態=無帯電が基準となる。それに対して 外周電子が抜けたか加わったか、によってプラスマイナスが決まる。 外周に束縛力の弱い電子が1個あっても、それが本来の外周電子ならば帯電はゼロである。 外周の電子がすべて安定に落ち着いていても、それが本来の電子の数よりも変化しておれば 帯電となる。
問題2
n型半導体は玉突き衝突に反応しやすい電子をもつために電流を通す機能において銅に似ている。 しかし、電流を通す機能がまったく同じわけではなく、少し違う点もある。それは何か?なぜ違うのか?
解説
銅は良導体。一方nが他半導体は半導体であり、電流に対して銅よりは抵抗がある。 その違いは、銅では、すべての原子が玉突き反応しやすい電子をもつのに対して、 n型半導体では、所々にあるリンの原子の部分だけが玉突き反応しやすい電子を 持つに過ぎないから。
問題3
p型半導体は玉突き衝突に反応しやすい電子をもたないが電流を比較的良く通す。それはなぜか?
解説
外周電子が1個少ない原子(=正孔)が所々にある。成功は自由電子を捕らえやすく、 また電位差が加わると放出しやすい。したがって成功を空き座席または飛び石のように利用して 自由電子の移動が起こるから。
問題4
接合型トランジスタのまん中のベース領域がもしエミッタ領域とかコレクタ領域と同程度の 厚みを持っていたならばトランジスタとしての増幅やスイッチ作用はどうなると思うか? またそれはなぜか?
解説
普通のコレクタにかける電圧(L)はベースにかける電圧(K)よりも高い。従ってベース/ コレクタの間では接合ダイオードに対して逆方向に電圧がかかる。その時ベースが分厚いと 下図のように接合Yで厚みのある空乏層B2,C1が出来る。 すると接合Xから侵入した電子がこの厚みを超えるための移動手段が無い。 (B2,C1に空き座席も玉突きも無い)
よってコレクタ回路には電流がまったく流れ図増幅動作もスイッチ動作もまったくしない。 ベースの厚みが非常に薄いとベース領域はB1しか存在しない。 (B2が出来るには、ベースに厚みが合って外部電圧につりあう帯電が 溜まる必要がある。)B1には電子が流通しそれがYを越えてコレクタ電流 となる。
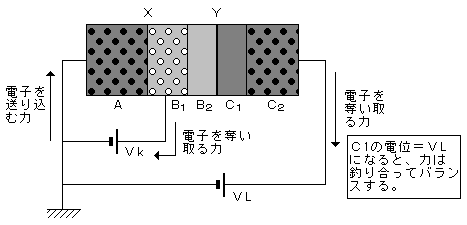
←トップへ
←授業選択画面に戻る
←鈴木研究室ホームへ