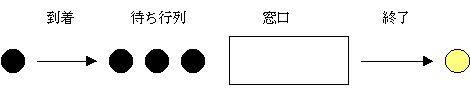待ち行列の説明
待ち行列とは
同じ種類のデータを一列に並べたデータ構造で、人間の順番待ちと同様に、最初に格納したデータが最初に取り出されるというもので、このしくみを
FIFO(先入れ先出し)と言います。
待ち行列の図
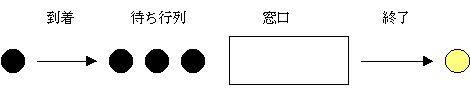
買い物やタクシー乗り場、駐車場や有料道路の料金所の例にも当てはめることができます。
ここでは銀行の預金・引出しの機械を例として考えます。
待ち行列の長さに影響を与える要因
●データ(お客さん)の到着間隔
○到着するデータ(お客さん)の間隔はどのような分布になるか
○データ(お客さん)は等間隔に来るのではない
●サービスの時間
○サービス時間はどのような分布になるのか
○サービスにかかる時間はお客さん
●窓口の数
○「サーバー数」といいます
といった要因が考えられます。
平衡状態と遷移確率
平衡状態kにある確率を
と書くと
ただし、
したがって、
の確率分布は以下の式より求まる。
ここで、ρ<1であれば
したがって、
より
が成り立つ。