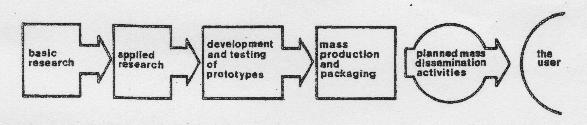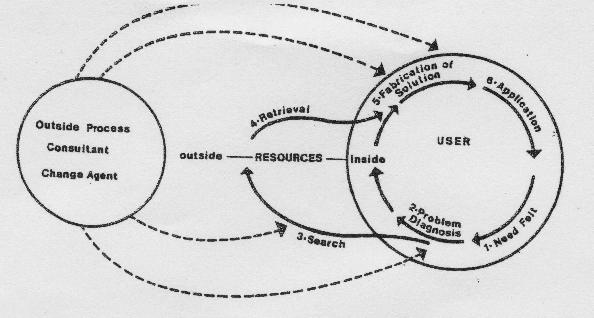第4回
今回は、普及モデルに関して行いました。前回に引き続き、何かと忙しい上にテンションが異様に低い(徹夜明けに作業してるから)ので、多少おかしい部分があるかもしれません。その内、余裕が出来たらヴァージョンアップします。
それでは、今回の講義ノートをどうぞ。
今回やる予定だったこと
(4)普及過程を促進する
1、「普及」をどう捉えるか?(ハベロックの4類系)
2、流行と「me,too-ism」
3、新しいことは良いことか?
4、ネットワーク人間 VS おたく族
「初年度につき要注意、と言ってある」とか言いつつ、先生が言い訳してました。認知的不調和、だそうです。 それでは、他に先生が言っていった事を幾つか簡単に書いておきましょう。 ・ブーメラン効果……自分の考えを補強するように解釈すること。先有知覚。 ・トレードオフ ……逃がした魚は大きい。認知的不調和において、どちらを重視するか?自分を納得させるか? ・フロンギトン説……辻褄あわせ。
1、ORDDモデル(図A-3)
※左から、「基礎研究」、「応用研究」、「プロトタイプ開発評価」、「大量生産」、「計画的大量普及活動」、「ユーザ」が訳。
・「計画的大量普及活動」はCMなどを指します。
・"Not invented-here"シンドローム…ここ(地元)で作られたものではないと拒否すること。
普及していても使ってもらえない?
→流れは分かりやすいが、そうそう上手くいかない。
○問題解決モデル(図A-1)
・各訳は以下の通り。
1.問題の意識、2.診断、3.情報検索、4.引き出す、5.解決策、6.適用
2、流行の6条件
以下の六つの条件が、流行の条件。
・新奇性 …めずらしさ
・顛末性 …くだらない
・無効用性…役立たない⇔表面的連帯感(サブカルチャー)
・選択性 …やってもやらなくてもよし
・短命性 …すぐ消える
・周期性 …繰り返す
「me,too-ism」
me-ism 米 個人主義
↑――→「me,too-ism」? 間人主義
we-ism 日 集団主義 私も〜〜(みんなと同じ)、説明しやすい。
3、鉛筆削りなどが例
・洋式トイレ
足が長くなって、足腰弱くなる?
・テレビ
各地の方言の画一化により、地方の差がなくなってきている。
・パック食品
ゴミが増える、主婦の料理ベタが増える。
4、ネットワーク人間 VS おたく族
ネットワーク人間かおたく族かの判定がありました。僕は5くらいだったので、普通でしょう。
ネットワーク人間とおたく族の違いは、能力・知識は同じでもやってることが違うことらしいです。
目次に戻る
第3回へ
第5回へ