やらせについてやらせはおそらく常識であり、5歩100歩か50歩100歩か、発覚するかどうかの差はあっても、どの番組にもあると思って間違いないだろう。
テレビとはそんなもの。それを覚悟して観るのが正しい姿勢と言うべきか。
もちろん、やらせが真実を含んでいないわけではない。ぶつぶつ不平を言っても情報を得るための手段として使わざるを得ないのもまた事実か。
授業風景を撮影教授に劣らぬヒゲのカメラマンが204講義室に現れ、授業風景を撮影していった。
二日酔いであまり寝ていないと主張する鈴木教授は、写真写りをとても気にするらしい。
彼が優雅に写っている姿をいっしょに願おう。
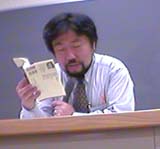
↑写真うつりを気にするシャイな鈴木先生
情報操作のやりかた民放各局は郵政省から5年おきに免許更新の認可を受けており、国家からの圧力を受けやすい。
民放連や各局の役員に郵政省からの天下りも多く、国策的な立場をとらざるをえなくなりがちだ。
最近の例では、辛口のコメンテーターをニュースに呼んでも、景気動向とかについて大したことは言わせられないとか、そういうことだろう。
与党の政策に批判的なことも言いにくい。批判はできても、否定はきわめてしにくい。
そのへんもわかったうえでテレビを見なければ、都合よく情報操作を受けるだろう。
メディアリテラシーを身に付けるというのは、きっとそういうことも含む。